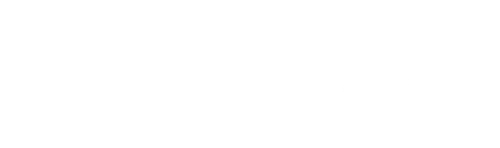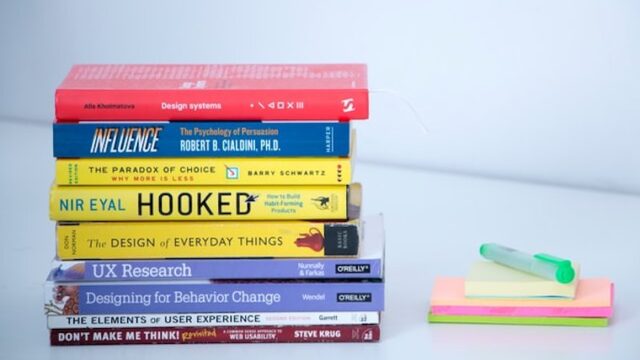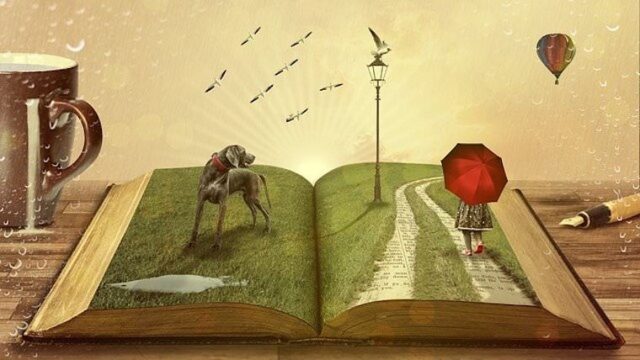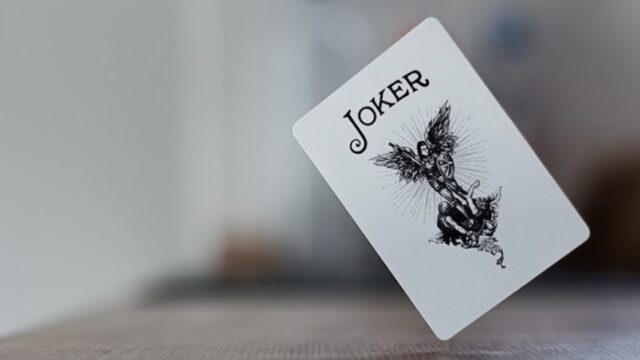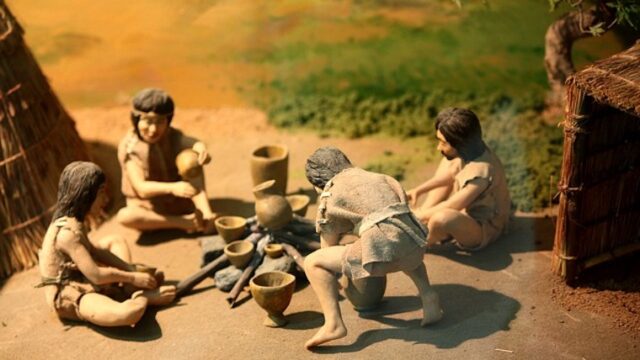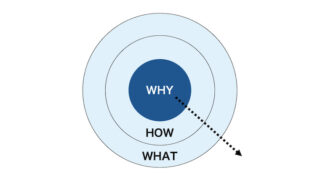- 同じ内容でも、話し手が変わると、信頼されなくなることがあります。
- 同じ内容でも、伝える順番が変わるだけで、台無しになってしまいます。
同じ内容なのに、なぜほんのちょっとの違いで結果が変わってしまうのでしょうか?ちょっと理不尽な気がしますが、これが現実です。
その秘密は「ハロー効果」にあります。ハロー効果は、第一印象の良し悪しによって、その人全体の印象が決まってしまう現象です。
この記事では次のことがわかります。
- ハロー効果とは何か?
- 見た目だけじゃないハロー効果の具体例
- ハロー効果を仕事に活用する方法
「見た目」「話し方」「資料の作り方」をちょっと変えるだけで、結果が劇的に変わります。ぜひチェックしてみてください。
ハロー効果とは?

ハロー効果(halo-effect)とは…
その対象(主に人)を評価するときに、たったひとつの顕著な特徴を見ただけで、他の特徴の評価もそれに引っ張られて同じ評価を受けてしまう現象のこと。
カンタンに言えば、
「評判のいい人がすることなら、何だって良いことだ!」
「悪名高い人がすることなら、何だって悪いことだ!」
と思い込んでしまう現象です。
心理学の用語であり、認知バイアスの一種です。同じく心理学で有名な「プライミング効果」の一種と考えられます。
文脈によって次の2つに大別されます。
| ポジティブ・ハロー効果 | 良い評価に引っ張られる現象 |
| ネガティブ・ハロー効果 | 悪い評価に引っ張られる現象 |
野球マンガでピッチャーが、「初球はインコースギリギリに攻めてビビらせてやるぜ!」なんて言っているのを見たことがあります。
これは第一印象で、「このピッチャーは甘い球は投げないぞ…キワどい球も振っていかないと…」というイメージを植え付けているワケですね。
一種のネガティブ・ハロー効果と言えるでしょう。
ハロー効果と「見た目」

ハロー効果は「見た目の第一印象で、その人の評価が決まってしまう現象」として知られています。実際には発言や文章でも起こりますが、確かに見た目が一番わかりやすいです。
ビシッとスーツを着た清潔感のあるビジネスマンは、仕事ができそうに見えます。言っていることもそれっぽく聞こえます。
逆にサイズが合ってないヨレヨレスーツのビジネスマンでは、イマイチ頼りなさそうです。言っていることも信じていいのか疑ってしまいます。
政治家がやたらと白髪を真っ黒に染めたがるのも、なるべく若々しく、力強い印象を与えるためです。
経歴詐称で干されてしまったショーンKさんは、彫りが深い顔立ちと、低く力強い声、きっちりした服装で、いかにも優秀なビジネスマンの出で立ちでした。彼を見る世間の目には、「ハロー効果」が強く効いていたと考えられます。
「見た目」だけじゃないハロー効果の事例

「ハロー効果」は何も見た目だけで起きる現象ではありません。2つの事例からハロー効果の本質を理解しましょう。
事例①:単語の並んだ順番が違うだけで人物評が変わる
ノーベル経済学賞を受賞した行動経済学者のダニエル・カーネマン氏の著書『ファスト&スロー』に登場する例をご紹介します。
突然ですが質問です。
次の人物の説明を見て、どちらが好きかお答えください。
| アラン | 頭がいい、勤勉、直情的、批判的、頑固、嫉妬深い |
| ベン | 嫉妬深い、頑固、批判的、直情的、勤勉、頭がいい |
いかがでしたでしょうか?
実は、ほとんどの人は「アラン」の方を好みます。
アランの印象
「頭がいいのか、それは良いことだ。しかも勤勉。感情が前面に出るタイプで意思が強い。そして負けず嫌い」
という印象ではないでしょうか?
一方のベンは、
ベンの印象
「嫉妬深く女々しい。しかも意地っ張りですぐに他人を批判する。すぐに不貞腐れる。頭はいいが理屈っぽい」
という印象ではないでしょうか?
すでにお気づきかもしれませんが、5つの単語は組み合わせは一緒で、並び順が違うだけです。
第一印象で抱いた感情により、後ろの単語の解釈が影響を受けてしまうのです。
事例②:最初の論文の出来が良いと、次の論文まで良く見える
こちらもダニエル・カーネマン氏の著書『ファスト&スロー』に登場する例です。
大学教授だったカーネマン氏が学生の論文を採点していたときの逸話です。論文には「課題1」と「課題2」があり、学生たちは2つの論文を綴じて提出します。
当初は1人ずつ採点していた
はじめは、同じ学生の論文を2つ続けて採点してから、次の学生の採点に移るやり方をしていました。しかしながら、採点中にある違和感を覚えました。
自身が同じ学生につける点数が、「課題1」と「課題2」で酷似していたのです。
1つ目の論文が良くできていると、2つ目の論文でよくわからない表現があっても良いように解釈して高い点数をつけてしまう。逆に1つ目の論文の出来が悪いと、2つ目の論文まで低い点数になってしまう。
本来は2つ論文を同じ重みで評価すべきなのに、1つ目の論文の方がはるかに重要になってしまっていたのです。
採点方法を変えたら…
やり方を変え、まず1つ目の論文を全員分採点したあとで、2つ目の論文を採点することにしました。
そうしたところ、1つ目の論文と2つ目の論文で、点数が大幅に違うケースが頻出するようになりました。
カーネマン氏は、採点方法を変えてしばらくは、自身の採点に一貫性が無さに不安を覚えていました。しかしながら、それでもこの採点方法がフェアであると結論づけています。
ハロー効果を仕事に生かす5つの方法

「ハロー効果」は、第一印象の良し悪しによって、その後の評価が歪んでしまう現象です。ビジネスで応用すれば、自分や商品の魅力をカサ増しできます。
ビジネスシーンで使えるハロー効果の5つの活用方法を紹介するので、参考にしてみてください。
活用①:ステレオタイプの見た目を意識する
1つ目の活用方法は、ベタに「見た目」にちなんだものです。
身なりを小ぎれいにするのはもちろんですが、併せて、その「職業」「職種」の典型的な見た目を意識してみましょう。
典型的な見た目の例
- 学者や小説家
:少し長めの白髪で、丸メガネをかける - 営業マン
:ダークカラーで体型にジャストフィットしたスーツ、おでこを出した爽やかな髪型 - 広告やメディア系
:ジャケパンスタイル、明るい色のシャツ - ITエンジニア
:Tシャツにジーンズ、ヒゲを生やして、ステッカーがたくさんついたMacを小脇に抱える
ハロー効果の一現象である「メラビアンの法則」によれば、話す内容と態度に矛盾がある場合は、「見た目>声のトーン>話す内容」の順で信頼が重みづけされます。
ステレオタイプな格好をするだけで、あなたの発言は信憑性を増すでしょう。少なくとも初対面の相手には効果ありです。
活用②:会話は否定から入らない
取引先や同僚と会話するときに、否定的な口調から入ると、以降の言動も否定的に捉えられてしまいます。
否定されたと感じた相手は不快感を持ち、その後のコミュニケーションがうまくいきません。わたし自身も20代前半の頃は、これで失敗してお客さんからこっぴどく叱られた経験があります。
当時わたしの尊敬していた上司がうまい言い回しをしていて、わたしもパクって使っているものがあります。
否定から入らないための言い回し
- 会話で相手がズレたことを言ってきたら、いったん「そうですよね。おっしゃる通りです。」と飲み込む
- 「確かにその考え方もあるんですが、実はもう一つこういう考え方もありまして…」と、切り出して、自分が話したい方向に持っていく
こうすれば、相手を否定したことにはなりません。自分の意見がまっとうであれば、相手も納得してその方向で話が進みます。
活用③:プレゼンは良い結論から話す
よくプレゼンは「結論から話せ」と言われますが、これは心理学的にも有効です。
そのプレゼンを採用した結果、どんなバラ色な変化が待っているか、冒頭のポンチ絵1枚で表現しましょう。良い内容から入れば、その後のプレゼンの内容も良い印象に映ります。
また、プロジェクトの承認を得ようとしているケースであれば、そのプロジェクトのリスクも報告しなければなりません。
そういうときはプレゼンの後半にリスクを載せておきましょう。前半のプレゼンが良ければ、前向きにリスクを乗り越えようと考えてくれるはずです。
活用④:資料の体裁は細部まで整える
「神は細部に宿る」という言葉をご存知でしょうか?
細かいところまで考え抜いて、手を尽くした人が勝つという意味です。元々は建築家の言葉ですが、ビジネスシーンでも使われます。
細部が手抜きのプレゼン資料を見たら、プレゼン内容も手抜きに感じてしまいます。損しないためにも、細部まで目を配りましょう。
資料で細部まで気にかけるべきポイント
- 資料に出てくる文字のフォントは揃える
- 色は統一感を持たせ、使う色はせいぜい2〜3色にする
- 要素のはみ出しに気をつける
- (垂直または水平の)矢印や線がちょっとでも斜めになっていないか気をつける
- 要素の間隔や位置を、整列機能を使って揃える
資料以外に、WEBサイトやアプリUIも同様です。もちろんお店の内装も。細部まで気配りしましょう。
活用⑤:有名人にあやかる
もはや心理学うんぬん以前の常識ですが、良いイメージの有名人を広告塔にすれば、商品のイメージも良くなります。その商品のイメージにあった芸能人やキャラクターを使うのももちろん有効です。
逆に言えば、その人の人間性とは関係なくても、不倫ドラマの記憶が新しい俳優さんを使うのは避けたほうがいいですね。
その他、次のような方法もハロー効果の恩恵にあやかれます。
その他のハロー効果の活用例
- その業界の権威(研究者、評論家など)に推奨してもらう
- 受賞歴をアピールする
- 利用者数を公開して、たくさん使われているとアピールする
- 良い口コミを前面に出す
共通点は、権威性をアピールしている点ですね。
≫【服従せよ】権威性=無条件で従わせる力。権威を獲得するコツを解説【実績0でも可】
まとめ

今回は心理学より「ハロー効果」を紹介しました。
ハロー効果とは…
- 第一印象の良し悪しによって、その人(またはもの)への評価が歪んでしまう現象
- 見た目だけではなく、言動や文章でも起こる
ハロー効果を仕事に活かす方法
- ステレオタイプの見た目を意識する
- 会話は否定から入らない
- プレゼンは良い結論から話す
- 資料の体裁は細部まで整える
- 有名人にあやかる
ハロー効果を活用すると、ちょっとした心がけで仕事が少しだけ上手くいきます。とにかく、第一印象はポジティブにいきましょう!
参考書籍
記事内で紹介している実験事例などは、行動経済学でノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマン氏の著書『ファスト&スロー』を参考にしています。
同書は、行動経済学のバイブル的な1冊(上下巻なので2冊ですが)となっています。人生にもビジネスにも、応用できるヒントが目白押しです。
「ハロー効果」は上巻に収録されています。
こちらは本聴き放題の「Audible」に対応しています。通勤・通学などの隙間時間で、手が塞がっていてもインプットできるので、本を読む時間が取れない人にはオススメです。
またAudibleは初回30日間無料。万が一合わなければ、解約すればコストはかかりません(それでも30日間はタダで本が聴けてしまいますが)。
本来なら聴き放題の対象になるような本ではないはず。ひょっとしたら、対象外になる日が来るかも…。早めのチェックをオススメします。
社会人の学びに「この2つ」は絶対外せない!
あらゆる教材の中で、コスパ最強なのが書籍。内容はセミナーやコンサルと遜色ないレベルなのに、なぜか1冊1,000円ほどしかかりません。
それでも数を読もうとすると、チリも積もればで結構な出費に。ハイペースで読んでいくなら、月1万円以上は覚悟しなければなりません…。
しかし現代はありがたいことに、月額で本読み放題のサービスがあります!
外せない❶ Kindle Unlimited
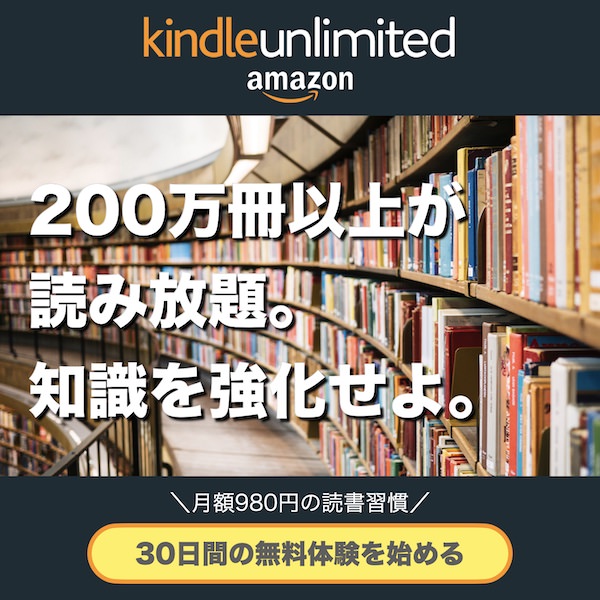
Amazonの電子書籍の読み放題サービス「Kindle Unlimited(キンドルアンリミテッド)」は、月額980円。本1冊分の値段で約200万冊が読み放題になります。
新刊のビジネス書が早々に読み放題になっていることも珍しくありません。個人的には、ラインナップはかなり充実していると思います。
外せない❷ Audible

こちらもAmazonの「Audible(オーディブル)」は、耳で本を聴くサービスです。月額1,500円で約12万冊が聴き放題になります。
Audibleの最大のメリットは、手が塞がっていても耳で聴けること。通勤中や家事をしながら、子供を寝かしつけながらでも学習できます。
冊数はKindle Unlimitedより少ないものの、Kindle Unlimitedにはない良書が聴き放題になっていることも多い。有料の本もありますが、無料の本だけでも十分聴き倒せます。
ちなみにわたしは両方契約しています。シーンで使い分けているのと、両者の蔵書ラインナップが被っていないためです。
どちらも30日間は無料なので、万が一読みたい本がなかった場合は解約してください(30日以内であれば、仮に何冊読んでいても無料です)。
そして読書は、早く始めた人が圧倒的に有利。本は読めば読むほど、複利のように雪だるま式に知識が蓄積されていくからです。
ガンガン読んで、ガンガン知識をつけて周りに差をつけましょう!
とりあえず両方試してみて、それぞれのラインナップをチェックするのがオススメです!