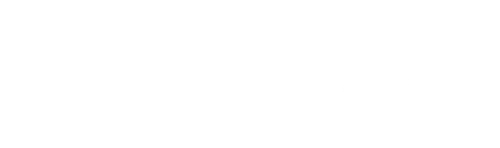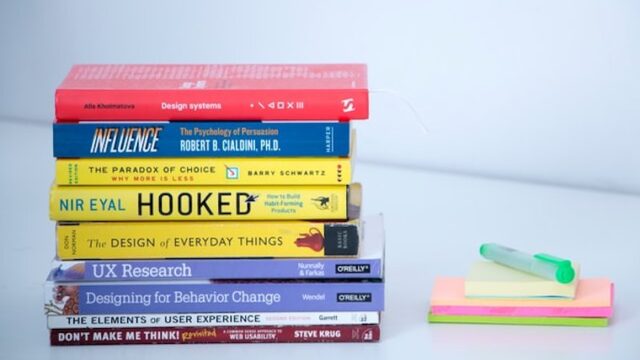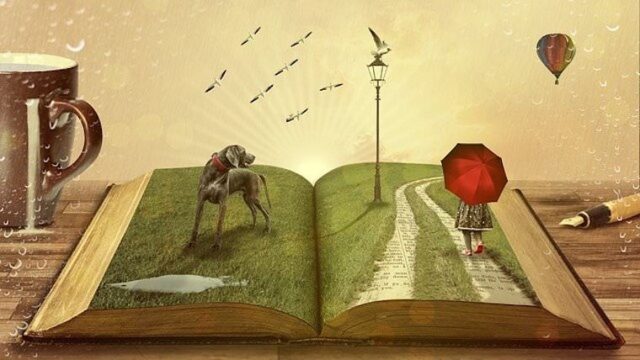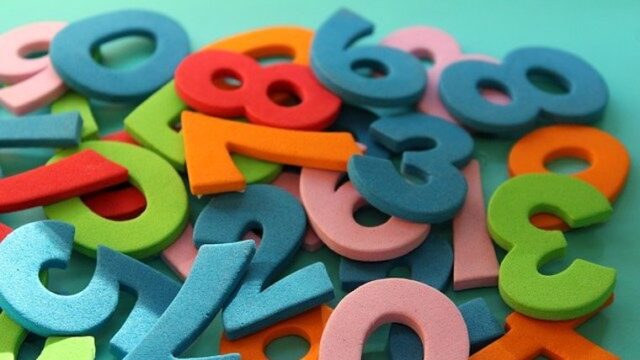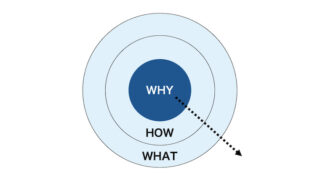やめたほうが良いとわかっているのに、ソシャゲをやめらない。多くの人が経験があるのではないでしょうか?
買ったビジネス書が役に立つか怪しくても、最後まで読んでしまう気持ち。ビジネスマンならわかりますよね?
このような心理を「サンクコスト効果」と呼びます。
サンクコスト効果とは、「これまでがんばってきたんだから、ここで辞めたらもったいない」と辞めるに辞められない気持ちになることです。
日常生活でも頻繁に見られる現象で、「もったいない」の感情は、サンクコスト効果から来るものが多いと思います。
ビジネスシーンでは、不採算投資を損切りできない現象が起きます。逆にサンクコスト効果の心理を逆手にとって、売上げを増やすことも可能です。
この記事では次のことがわかります。
- サンクコスト効果と何か?
- 秘密は「損失回避性」!サンクコスト効果が起こる原因とは?
- サンクコスト効果が経営判断を誤らせる事例
- サンクコスト効果を逆手にとって、リピート顧客を狙うアイデア
投資をしている人や、経営に携わっている人は、絶対に押さえておきましょう!
サンクコスト効果とは?

サンクコスト効果(sunk cost effect)とは…
あるものに対し、時間や費用を投資し続けることが損失につながる可能性が高いのに、「もったいないから」と感じてやめられなくなってしまう現象のことです。
行動経済学や心理学で使われる用語です。
「サンクコスト」とは、すでに投資してしまって、戻ってこないお金のことです。経済学用語です。日本語では「埋没費用」と呼びます。
身近に起きるサンクコストの例

サンクコスト効果は、あなたの身近にたくさん潜んでいます。
次のような経験はありませんか?
例①:ソシャゲをやめられない
なかなかやめられずに、年単位で同じソシャゲをプレイしている人は多いと思います。すごく楽しいわけじゃないのに、なんだかやめられない。そんな気分ではないでしょうか?
そのゲームに費やしてきた時間が長ければ長いほど、サンクコスト効果で、「ここまで育ててきたのにやめるのはもったいない」と感じるようになります。
課金をしていれば、尚更やめられません。「ここまでウン万円も費やしてきたのに、やめたら何も残らない」と感じます。
例②:買った本が面白くなくても最後まで読む
ビジネス書をいざ読み始めたら、期待してした内容とは違い、イマイチ役に立たなそうに感じることがあります。
こんなときは、「せっかくお金を払ったんだから」と、最後まで読もうとしてしまいがちです。
マンガ雑誌を買っていると、そこまで好きじゃない漫画でも、「せっかく買ったんだから」と読んでしまう。これも同様の現象です。
例③:ギャンブルは負けたままでは終われない
負けたままその日のギャンブルをやめてしまうと、それまでに賭けてきた資金が全てムダになったように感じます。
ですが、ギャンブルを終了させなければ、まだムダは確定していません。せめてプラスマイナスゼロまでは取り返したいと思い、負けたままギャンブルを継続してしまいます。
どうでしょうか?経験ありますよね?
サンクコスト効果を乗り越えるためには、過去の投資は帰ってこないものと割り切り、未来のことだけ考えて最善の選択をする必要があります。
過去いくらつぎ込んだソシャゲであろうと、この先に費やす時間とお金に見合わないのであれば、すっぱりやめるべきでしょう。
サンクコスト効果の原因は「損失回避性」にあり

サンクコスト効果の原因は、人間の「損失回避性」にあります。
人間には、何かを得る喜びより、何かを失う悲しみの方が2倍ほど大きく感じる性質があります。1万円を拾った喜びの大きさと、2万円落とした悲しみの大きさが、同じくらいに感じます。
そのため、損失が確定する状況を受け入れることに、強い嫌悪感を感じます。これまで投じた時間や費用がムダだったと認めたくないので、ズルズルとやめられなくなってしまいます。
ギャンブルであれば、負けてマイナスが出ている状況でも、ギャンブルを止めるまでは損失は確定しません。
ギャンブルを続けている限り、(可能性は低くても)逆転のチャンスはあるので、損失を受け入れてやめることができないのです。
損失回避性によって起こる行動は、行動経済学で有名な「プロスペクト理論」で体系化されています。金融トレーダーが心理に惑わされて運用を失敗しないためのバイブルにもなっています。
≫ プロスペクト理論とは?具体例と図でわかりやすく超丁寧に解説
実際にあったサンクコスト効果の事例「コンコルド」

サンクコスト効果は、「コンコルド効果」とも呼ばれています。その名の由来となった事例を紹介します。
コンコルドは、1969年にフランスとイギリスが共同開発した超音速旅客機。世界初の超音速(マッハ2.0 約2,400km)で航行でき、見た目も未来を感じさせるもので、当時は大注目を浴びました。
しかしながら、デメリットもかなりありました。
- 開発費が高額
- 燃費が悪い
- 乗客100人しか乗れない
- 長い滑走路が必要
- 騒音が大きい
といったマイナス要素で、需要は一気に下がってしまいます。
ビジネスで採算を取れる見込みは限りなく薄く、プロジェクトを中止して、注文が入っていた航空会社に賠償金を払ったほうが安く済む状況でした。
しかしながら、経営判断は「プロジェクト継続」でした。
今まで投入した予算や時間が全て水泡に帰すことに加え、責任の押し付け合いとなったため、ズルズル開発を続けることになったのです。
その結果、コンコルドを開発した会社は莫大な損失を計上し、倒産してしまいました。
サンクコスト効果を反面教師にしたいシーン3選

あなたの身の回りにある、断ち切るべきサンクコスト効果の過ちを3つ紹介します。
シーン①:株の損切りができない
株の損切りができないのは、サンクコスト効果の典型例です。
損失が確定する状況を避けるため、取得価額を下回った株式を売却できなくなることを、「損切りできない」と呼びます。
本来であれば、下がっている株式は早めに売却したほうが良いのですが、そうすると損失が確定してしまいます。
株を持ち続けていれば損失は発生しないので、そのまま下り坂の株式を持ち続けて、さらに損失を膨らませる結果になります。
また、「儲けが出ている株」と「損失が出ている株」がある場合に、儲けが出ている方を売却して、利益を確定させようとしがちですが、これも誤りですね。
単純に上がる可能性が高い株を売却しているのも問題ですが、税金の観点でも不利になります。損失が出ている株は売却しても課税されないので、そっちを処分すべきでしょう。
シーン②:見込みのない事業に投資を続けてしまう
不採算事業を継続してしまうのも、本質的には株の損切りができないことと同じです。
上手くいっていない事業をここでやめてしまえば、これまでの投資の損失が確定します。これまでかけてきた時間も人員もムダだった認めることになります。
そのため多くの企業は、黒字化の見込みが薄い不採算事業であっても、追加投資で逆転のチャンスに賭けようとする傾向があります。
シーン③:長年勤めた会社をやめられない
イヤな職場でも、「ここまでこの会社で働いてきたし、他の会社で1から実績積むよりも出世できそうだから…」と、なんとなく転職できずにいる人が多いと思います。
こんな人は、これまで会社に費やしてきた時間と実績が「サンクコスト」になっています。
終身雇用時代は、一度会社を辞めると生涯賃金が下がるので、イヤな職場でも耐え忍ぶ意味はありました。でも、現代では終身雇用神話は崩壊しています。
もう少し自分に正直になっても良いのかもしれません。また今は待遇が良くても、長い目で見て斜陽な業界なら、早めに切るべきでしょう。
サンクコスト効果を逆手にとった継続のコツ

サンクコスト効果は、「『もったいない』と思って、ズルズル続けるのはやめよう!」という文脈で語られることがほとんどです。
ですが、サンクコスト効果があるものとして、逆手に取ることで、あなたがダイエットなり勉強なり、何かを継続させる手助けもできます。
継続のコツ①:続けることが続けるコツ
「何を言っているんだ?」と思われたかもしれませんが、大真面目です。
マラソン大会に参加しているシーンを想像してください。スタートから5km付近で急に辛くなってきたら、あなたは途中棄権してしまうかもしれません。
それが40km付近だったらどうでしょうか?きっと死に物狂いでゴールしようとするはずです。だって、ここまで頑張ってきたんですから。
今回の例の場合は、「ここまで頑張って続けてきた!」というサンクコスト効果の他に、ゴールが近づくほどやる気が出る「目標勾配仮説」も影響しています。
長く続けつつ、目標(ゴール)まで近づいていることが、辞めづらくさせる最大のコツではないでしょうか。
継続のコツ②:初期投資をガッツリしてしまう
もしあなたにどうしても続けたいことがあるなら、思い切って初期投資に大きなお金を投じてみましょう。ガッツリ形から入るのです。
初期投資で大きな金額を突っ込んだ挙句、早々に辞めてしまってはもったいないですよね。そのサンクコスト効果を逆手に取って、辞めづらい環境を作ってしまう作戦です。
継続のコツ③:本は自腹で買う
読書は大事な習慣の一つですが、なかなか読み進められずに挫折してしまう人が少なくないのではないでしょうか?
一つ前のコツと同じ話ですが、本は自腹で買った方が挫折しづらいでしょう。言わずもがな、買ったのに読まなければもったいないからです。読む際の真剣味も、自腹の方が強いように感じます。
本は学校や会社で回覧したり、知人から借りたりと、タダで読める機会が少なくありません。ですが、ここは自己投資と思って自腹での購入を強くオススメします。
ただ役に立たないと気がついても、もったいなくて読み続けてしまう負の側面もあります。ここは折り合いをつける必要がありますが、トータルで考えると、やっぱり自腹で買った方が身になります。
サンクコスト効果を活用したビジネス事例

サンクコスト効果は、人間の脳に染み付いた思考パターンです。意識していない限り、避けるのは困難。
そんなサンクコスト効果をしたたかに活用したビジネスもよく目にします。3つ事例を紹介します。
事例①:毎号付録がついてくる雑誌
「デアゴスティーニ♪」のフレーズでお馴染みの、あの雑誌です。雑誌には毎号付録がついていて、実際のところ本よりも付録が主役という変わったビジネスモデルです。
付録はパーツになっていて、全部の号を購入すると付録が完成する仕組みです。途中で購読をやめればこれまで買ってきたパーツは完成せず、中途半端なガラクタにしかなりません。
そのため、購読をやめるのを踏みとどまらせる効果があります。
事例②:航空会社のマイレージサービス
航空会社のマイレージサービスは、顧客のロイヤルティーを高める非常によくできたプログラムです。
年間100,000ポイント達成すれば、来年は最上位クラスの待遇を受けることができます。11カ月目で、自分がいま90,000ポイントだったらどう思うでしょうか?
ここまで90,000ポイント分、飛行機に乗るという一種の投資をしてきています。ここでやめたらもったいないですね。
ポイント稼ぎのために、日帰りで北海道に海鮮を食べに行く人が続出するのも納得です。
事例③:Amazonプライムの年会費
いまはAmazonプライムにも月額払いがありますが、元々は年払い一択でした。
1度Amazonプライムに加入すれば、向こう1年間は使おうが使わまいが、コストは変わりません。つまり「サンクコスト」になります。
そんなときに、他社でもっと良いサービスが出たらどうなるでしょう?
「いや、もう1年分の料金を払っちゃったから、当分はAmazonプライムを使おう。更新時にまた考えよう」ってなりますよね。
会員費サービス全般に共通します。「コストコの会員費払っちゃってるから、コストコで買おう」って思います。顧客を縛り付けるには、会員サービスが有効です。
まとめ

今回は行動経済学より「サンクコスト効果」をご紹介しました。
次の通りまとめます。
サンクコスト効果とは…
あるものに対し、時間や費用を投資し続けることが損失につながる可能性が高いのに、「もったいないから」と感じてやめられなくなってしまう現象のこと
サンクコスト効果を反面教師にしたいシーン
- 株の損切りができない
- 見込みのない事業に投資を続けてしまう
- 嫌なのに、長年勤めた会社をやめられない
サンクコスト効果を活用したビジネスアイデア
- 毎号付録がついてくる雑誌
- 航空会社のマイレージサービス
- Amazonプライムの年会費
日本人の美徳とされる「もったいない」。
食べ物を大事に残さず食べる「もったいない」は良いことですが、ことリソース配分に関しての「もったいない」はあなたをジリ貧にさせるかも。
「これ、続ける意味あるのかなぁ」と感じたら、思い切って損切りを検討しましょう。
関連記事
サンクコスト効果を引き起こす「損をしたくない気持ち(損失回避性)」は、行動経済学の世界では非常に強い作用の一つです。
損失回避性を体系的にまとめた「プロスペクト理論」を知っていると、さらに本質的な理解につながります。本質的な理解は、応用の幅を広げるので、ぜひチェックしてみてください。

社会人の学びに「この2つ」は絶対外せない!
あらゆる教材の中で、コスパ最強なのが書籍。内容はセミナーやコンサルと遜色ないレベルなのに、なぜか1冊1,000円ほどしかかりません。
それでも数を読もうとすると、チリも積もればで結構な出費に。ハイペースで読んでいくなら、月1万円以上は覚悟しなければなりません…。
しかし現代はありがたいことに、月額で本読み放題のサービスがあります!
外せない❶ Kindle Unlimited
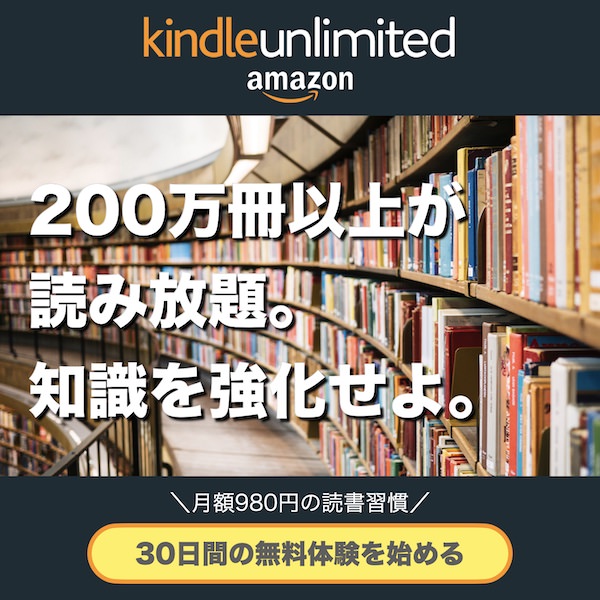
Amazonの電子書籍の読み放題サービス「Kindle Unlimited(キンドルアンリミテッド)」は、月額980円。本1冊分の値段で約200万冊が読み放題になります。
新刊のビジネス書が早々に読み放題になっていることも珍しくありません。個人的には、ラインナップはかなり充実していると思います。
外せない❷ Audible

こちらもAmazonの「Audible(オーディブル)」は、耳で本を聴くサービスです。月額1,500円で約12万冊が聴き放題になります。
Audibleの最大のメリットは、手が塞がっていても耳で聴けること。通勤中や家事をしながら、子供を寝かしつけながらでも学習できます。
冊数はKindle Unlimitedより少ないものの、Kindle Unlimitedにはない良書が聴き放題になっていることも多い。有料の本もありますが、無料の本だけでも十分聴き倒せます。
ちなみにわたしは両方契約しています。シーンで使い分けているのと、両者の蔵書ラインナップが被っていないためです。
どちらも30日間は無料なので、万が一読みたい本がなかった場合は解約してください(30日以内であれば、仮に何冊読んでいても無料です)。
そして読書は、早く始めた人が圧倒的に有利。本は読めば読むほど、複利のように雪だるま式に知識が蓄積されていくからです。
ガンガン読んで、ガンガン知識をつけて周りに差をつけましょう!
とりあえず両方試してみて、それぞれのラインナップをチェックするのがオススメです!