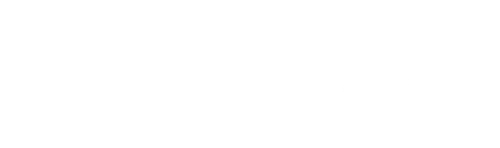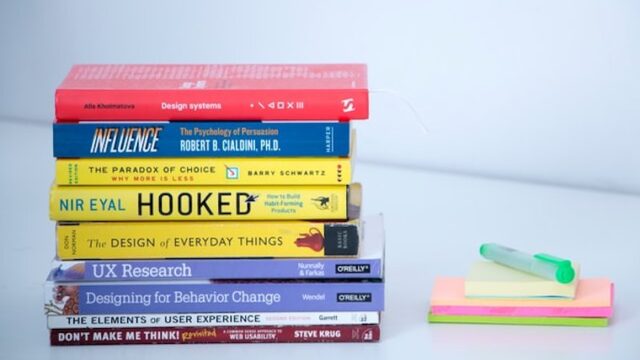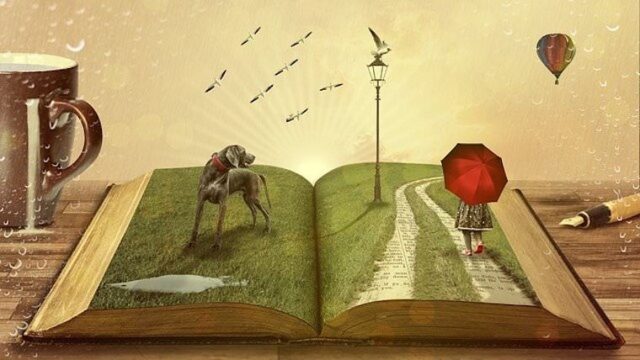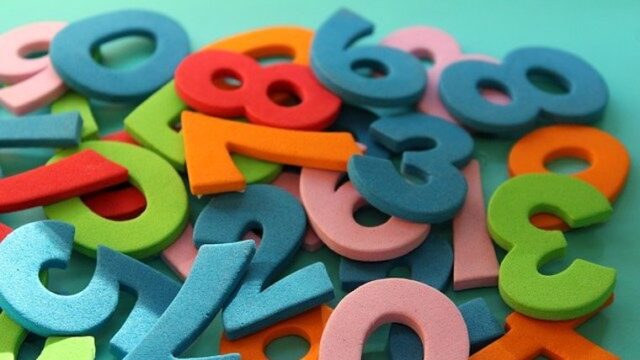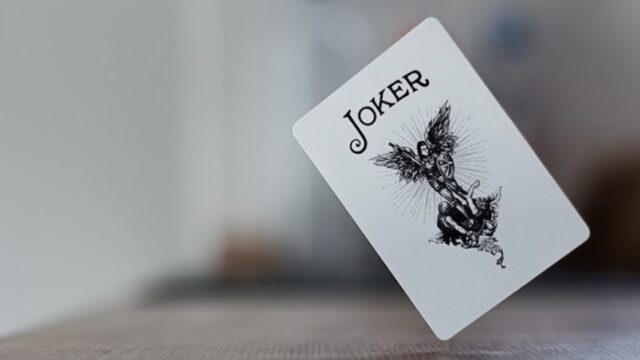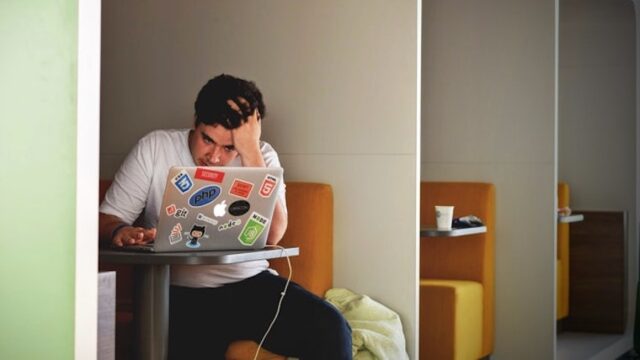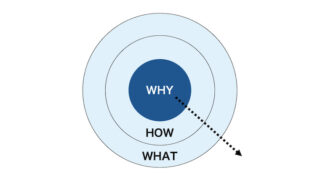「代表性ヒューリスティック」は、その分野の中でステレオタイプだと思う事柄の発生確率を、過大評価してしまう意思決定プロセスのことです。
その結果、陥ってしまう判断ミスを「連言錯誤」と呼びます。
行動経済学における重要概念であるヒューリスティック。その中でもメジャーな1つに数えられるのが代表性ヒューリスティックです。
ビシッとしたスーツを着た爽やかな営業マンが信頼できると思ってしまう現象も、代表性ヒューリスティックによるものです。
この記事でわかること
- 代表性ヒューリスティックとは何か?
- 連言錯誤はどういう関係?
- 実験事例
- ビジネスで活用する方法
人間の心理は、ときに理不尽な結果をもたらします。代表性ヒューリスティックもその一つです。賢く仕事に活かしていきましょう。
代表性ヒューリスティックとは?
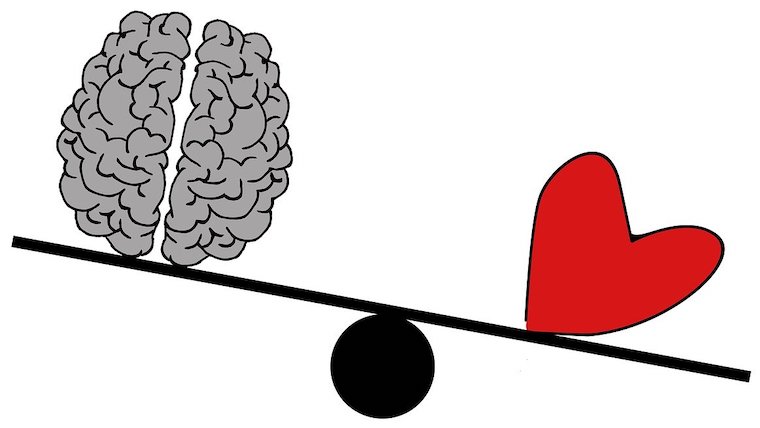
代表性ヒューリスティック(representativeness-heuristic)とは…
代表的・典型的だと思う事柄の発生確率を過大評価してしまう意思決定プロセスのことです。
行動経済学の用語です。
「代表性ヒューリスティック」で考えた結果、一般的に起こる状況よりも、もっともらしく思える限定された状況の方が、事実らしいと勘違いすることがあります。
この勘違いを、「連言錯誤(れんごんさくご)」または「合接の誤謬(ごうせつのごびゅう)」と呼びます。こちらは認知バイアスの一種です。
そもそも「ヒューリスティック」って何なの?
「ヒューリスティック(heuristic)」は、一般的な用語ではないので、ほとんどの人にとって聞きなれないと思いますが、行動経済学では非常に重要な概念です。
超端的に言えば、カンタンに解けない複雑な問題に対し、自分で解けそうなよりカンタンな問題に置き換えて考える思考プロセスのことです。
脳は考える度にエネルギーを消費しますが、エネルギーは有限です。節約しないとすぐにガス欠になって、使い物にならなくなります。
そうならないために、脳は深い思考が必要じゃないシーンでは、経験則と直感を使ってなるべく深く考えないようにしています。
ヒューリスティックで出した回答は、日常生活の大抵のシーンでは問題ないのですが、しばしば間違った判断をしてしまいます。
ヒューリスティックをもっと詳しく知りたい人は、こちら↓もチェックしてみてください。
≫ ヒューリスティックとは?バイアスとの違いは?具体例で解説
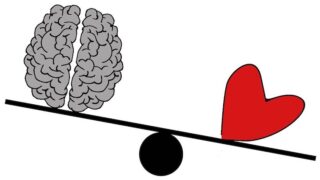
例題で学ぶ代表性ヒューリスティック&連言錯誤

代表性ヒューリスティックは説明だけだとわかりづらいので、例題を見てもらいたいと思います。
次の問題を見てみてください。
学生が多い街中のコンビニで万引き事件がありました。次のどちらが犯人の可能性が高いと思いますか?
A:近所の高校生
B:コンビニから一番近い高校の不良グループ
直感では「Bの不良グループがやったに違いない」と思いましたよね。
冷静に考えてみると、「B:コンビニから一番近い高校の不良グループ」は「A:近所の高校生」に含まれます。AよりBの確率が高いことはありえません。
この問題に直面した人の脳は、「どちらが犯人の確率が高いか?」ではなく、「どちらがより、犯人を代表するイメージに近いか?」という問題に置き換えて考えています。
その結果、「Bの不良グループが万引きした」と思ってしまうのです。
例題を深掘り解説
「代表性ヒューリスティック」は、基準となる確率を無視して、「その事柄が、自分の持つステレオタイプのイメージとどれだけ似ているか?」という問題に置き換えて判断する思考プロセスです。
この問題では、「どちらが、自分の中にある犯人のイメージに似ているか?」と考えた部分が、「代表性ヒューリスティック」に当たります。
「連言錯誤」は、一般的に起こる状況よりも、もっともらしい限定された状況の方が、事実だと勘違いする認知バイアスです。
この問題では、「近所の高校生に当てはまる人数の方が多いのに、少人数しか当てはまらない不良グループが犯人の可能性が高い」と勘違いした部分が、「連言錯誤」に当たります。
代表性ヒューリスティックの実験事例
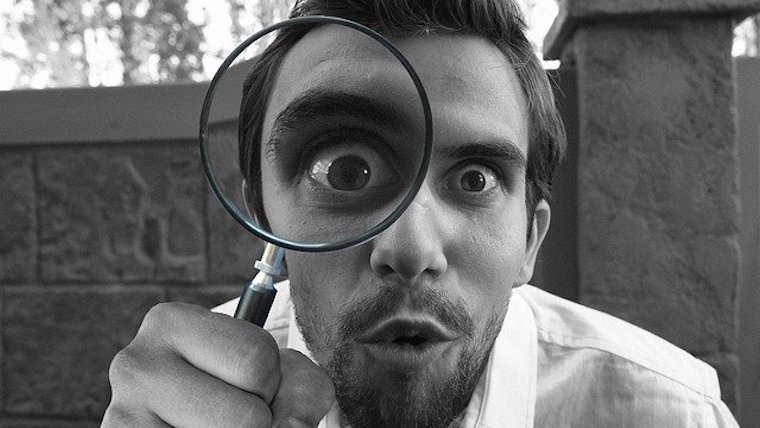
続いて、「代表性ヒューリスティック」の実験事例を見ていきましょう。
実験事例①:リンダ問題

代表性ヒューリスティックの実験で、もっとも有名なのが「リンダ問題」です。いろんなところで目にする機会があるので、教養として知っておいて損はありません。
実験の内容
被験者に、次の文章を読んでもらう。
リンダは31歳の独身女性。外向的でたいへん聡明である。専攻は哲学だった。学生時代には、差別や社会正義の問題に強い関心を持っていた。また、反核運動にも参加したことがある。
その上で、現在のリンダは、以下のどちらの可能性がより高いか答えてもらう。
- A:リンダは銀行員
- B:リンダはフェミニストな銀行員
先程の例題でタネはバレているので、オチが見えてしまったかもしれませんね。結果に移りましょう。
実験の結果
実験の結果、80%超の被験者が、「B:リンダはフェミニストな銀行員」と回答した。
「フェミニストな銀行員」は、「銀行員」の一部です。冷静に考えれば、「フェミニストな銀行員」の方が確率が高いことありえないとわかったはずです。
被験者はこの問題を、「リンダの人物像は、『銀行員』と『フェミニストな銀行員』のどちらのステレオタイプに近いか?」という質問に置き換えていたと考えられます。
リンダの人物説明が、フェミニストのステレオタイプに一致することから、被験者は誤った回答を出してしまったのです。
実験事例②:サイコロで同じ目は連続しない?

ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマン氏の著書『ファスト&スロー』に出てくる例題を紹介します。実験事例ではありませんが、非常にわかりやすい例題です。
次の問題を考えてみてください。
問題
4つの面を緑、残り2つ面を赤く塗ったサイコロがあるとします。
このサイコロを20回振ったとき、次の3つで一番起きそうな目の順番はどれでしょう?
- A:赤緑赤赤赤
- B:緑赤緑赤赤赤
- C:緑赤赤赤赤赤
Bが一番起きそうに思いませんか?「緑」が2回出てくるので、いくらか確率が高そうに見えます。
AとCは「赤」がたくさん出てくるので、あまり代表的な目には見えません。
実は「B:緑赤緑赤赤赤」は、「A:赤緑赤赤赤」の頭に「緑」をつけただけです。そのため、BがAより確率が高いことはありえません。
このような、ある事象の発生頻度が特定の期間中に高かった場合に、その後のその事象の発生頻度を低く見積る傾向は、「ギャンブラーの誤謬(gambler’s fallacy)」と呼ばれています。
ギャンブラーの誤謬は、代表性ヒューリスティックによって起こる認知バイアスです。
テストの選択問題で、「A」の回答が3回続いたら、次の問題は「A」じゃないだろう思ってしまいますね。これもギャンブラーの誤謬によるものです。
実験事例③:ディナーセットの価格づけ実験

シカゴ大学のクリストファー・シー氏が、地元のお店の在庫一掃セールで売られているディナーセットで行った実験です。
やや変則的な感じですが、非常に面白い結果になっています。
実験の内容
2種類のディナーセットを用意する。
被験者を3グループに分け、2種類のディナーセットに値段をつけてもらう。
| セット① | ||
| 種類 | 枚数 | 状態 |
| ①大皿 | 8枚 | 全て良好 |
| ②スープ/サラダ用深皿 | 8枚 | 全て良好 |
| ③デザート皿 | 8枚 | 全て良好 |
| ④コーヒーカップ | 8枚 | うち2個損傷あり |
| ⑤ソーサー | 8枚 | うち7枚損傷あり |
| セット② | ||
| 種類 | 枚数 | 状態 |
| ①大皿 | 8枚 | 全て良好 |
| ②スープ/サラダ用深皿 | 8枚 | 全て良好 |
| ③デザート皿 | 8枚 | 全て良好 |
「セット①」と「セット②」の違いは、コーヒーカップとソーサーが有るか無いか。
「セット①」は「セット②」の内容を全て含んでいます。「セット①」の方が、いくらか価値は高いはずですね。
被験者グループの条件
- グループA
:セット①と②の両方を見て、両方の値段をつけてもらう - グループB
:セット①だけ見て、セット①の値段をつけてもらう - グループC
:セット②だけ見て、セット②の値段をつけてもらう
グループAは、両方を見比べて、「並列」で評価しました。
グループBとグループCは、片方だけ見て「単独」で評価を下しました。
実験の結果
結果は次の通りです。
- A:セット①を32ドル、セット②を30ドル
- B:セット①を23ドル
- C:セット②を33ドル
とそれぞれ値段をつけた。
さすがに両方見たグループAは、欠けがあったとしても「セット①」の方が、少し価値が高いと判断しました。妥当な判断です。
片方しか見ていないグループBとCは、点数が少ない「セット②」の方に高い値段が付きました。「セット①」は不完全なカップとソーサーを抜いたほうが高く売れるという不思議な結果です。
ディナーセットは全て揃っているのが代表的な(当たり前の)姿なので、欠けたカップとソーサーによって、価値を下げられてしまったわけです。
代表性ヒューリスティックをビジネスに活用する方法 5選

「代表性ヒューリスティック」のなんぞやは、もうわかりましたね。続いて、「代表性ヒューリスティック」を仕事で活用するためのヒントを5つ紹介していきます。
活用①:オフィスやホームページを綺麗にする
GoogleやAppleのオフィスをメディアで見たことあるはでしょうか?
すごくキレイなオフィスで、テーマパークみたいに色んな趣きの部屋があります。ホームページも洗練されています。綺麗なオフィスやホームページは、先進的な企業の代表例として認知されています。
実際の事業の中身はさておいて、オフィスやホームページの見た目を綺麗にするだけで、あなたの会社も先進的だと思ってもらいやすくなります。
オフィスは賃貸契約が多いので、カンタンに内装を変えられないかもしれません。そういうときはオシャレなコワーキングスペースを借りておいて、来客時はそこを使うのもアリですね。
活用②:ステレオタイプな見た目を意識する
営業マンであれば、パンフレットに載っているモデルさんのように、爽やかで、ビシッとスーツを着ている人が代表的なイメージです。
代表的なイメージに合わせるだけで、あなたの発言は「できる人」の発言だと思ってもらえます。(最初だけですが)
ただし、みんながみんなフォーマルな格好しているから良いというわけではありません。
初めて会ったデザイナーさんが、スーツに七三分けのヘアスタイルだったら、「この人ホントに大丈夫かな?」と心配になります。奇抜な髪型で個性的な服装の方が、むしろ安心できます。
職業にあったステレオタイプの見た目を意識しましょう。
活用③:パッケージ販売は完全なセットで
ディナーセットの例で見たように、本来セットが一般的な商品に欠けがあると、著しく価値が落ちてしまいます。
わたし自身も経験があります。趣味でスニーカーを集めているのですが、アフターマーケットでは、箱や付属の変え紐があるかないかで値段が随分変わってしまいます。
2万円で売られているスニーカーでも、箱がないと1万6,000円になったりします。これは個人的な価値観とも一致します。でも「箱に4,000円払うか?」と言われればNOです。ここが人間心理の不思議なところ。
というわけで、パッケージ販売する場合、中途半端に「〇〇は別途購入してください」という販売の仕方は、価値を下げていることになります。
このパッケージさえ買えば全部OK、他は何も買う必要なし。という風にしましょう。
活用④:製品の機能は、足すのではなく削る
家電やWebサービス、スマホアプリは、機能を足して便利したい誘惑に駆られます。一見すると、機能はたくさんある方が優れているように感じます。
しかし機能を足せば足すほど、その製品が何を代表するものなのか、わからなくなってしまいます。製品のコアとなる機能以外を削ぎ落とす方が、実は価値が上がるのです。
Kindleを例にしてみましょう。Kindleは本を読むためのデバイスに特化しています。通常タブレットについている機能を削り、カラーディスプレイも削っています。
機能が削ぎ落とされた結果、
- バッテリーの持ちが良い
- 目に優しいディスプレイで長時間見ても疲れない
- 安価
という読書に最適なデバイスとなり、大ヒットしました。
活用⑤:大手だからという理由だけで判断しない
- 大手企業が始める新サービスだからきっと成功する
- 大手企業は業界の代表なので、ここの提案を受けておけば安心だ
そんなイメージがあるかもれませんが、決してそんなことはありません。
Appleだって、Googleだって、Amazonだって失敗した事業は普通にあります。どんな大手だろうと、プロジェクトが何一つトラブルなく終わったなんて聞いたことありません。
代表的な企業だからといって、本来の成功確率を無視すると、手痛いしっぺ返しを喰らいます。そもそも新しい事業は失敗する確率が高いし、プロジェクトはトラブルが起きるものです。
投資するにしても、プロジェクトを任せるパートナー選ぶにしても、複数社を候補として、ネームバリューではなく実力で評価しましょう。
まとめ
今回は行動経済学より「代表性ヒューリスティック」を紹介しました。
代表性ヒューリスティックとは…
- 基準となる確率を無視して、「その事柄が、自分の持つステレオタイプのイメージとどれだけ似ているか?」という問題に置き換えて判断すること
連言錯誤とは…
- 代表性ヒューリスティックで判断した結果、陥ってしまう認知バイアス
- 一般的な状況よりも、もっともらしく思えるより限定された状況の方が、事実らしいと勘違いすること
代表性ヒューリスティックはわかりづらい概念ですが、この記事で理解が深まれば嬉しく思います。
参考書籍
記事内で紹介している実験事例などは、行動経済学でノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマン氏の著書『ファスト&スロー』を参考にしています。
同書は、行動経済学のバイブル的な1冊(上下巻なので2冊ですが)となっています。人生にもビジネスにも、応用できるヒントが目白押しです。
「代表性ヒューリスティック」は上巻に収録されています。
こちらは本聴き放題の「Audible」に対応しています。通勤・通学などの隙間時間で、手が塞がっていてもインプットできるので、本を読む時間が取れない人にはオススメです。
またAudibleは初回30日間無料。万が一合わなければ、解約すればコストはかかりません(それでも30日間はタダで本が聴けてしまいますが)。
本来なら聴き放題の対象になるような本ではないはず。ひょっとしたら、対象外になる日が来るかも…。早めのチェックをオススメします。
社会人の学びに「この2つ」は絶対外せない!
あらゆる教材の中で、コスパ最強なのが書籍。内容はセミナーやコンサルと遜色ないレベルなのに、なぜか1冊1,000円ほどしかかりません。
それでも数を読もうとすると、チリも積もればで結構な出費に。ハイペースで読んでいくなら、月1万円以上は覚悟しなければなりません…。
しかし現代はありがたいことに、月額で本読み放題のサービスがあります!
外せない❶ Kindle Unlimited
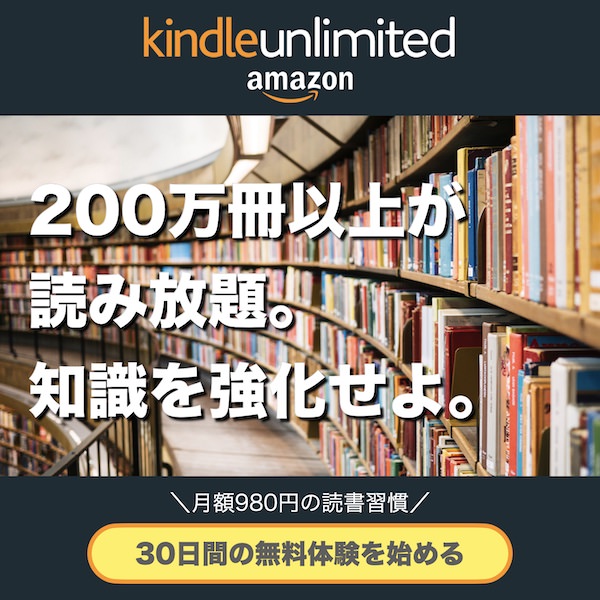
Amazonの電子書籍の読み放題サービス「Kindle Unlimited(キンドルアンリミテッド)」は、月額980円。本1冊分の値段で約200万冊が読み放題になります。
新刊のビジネス書が早々に読み放題になっていることも珍しくありません。個人的には、ラインナップはかなり充実していると思います。
外せない❷ Audible

こちらもAmazonの「Audible(オーディブル)」は、耳で本を聴くサービスです。月額1,500円で約12万冊が聴き放題になります。
Audibleの最大のメリットは、手が塞がっていても耳で聴けること。通勤中や家事をしながら、子供を寝かしつけながらでも学習できます。
冊数はKindle Unlimitedより少ないものの、Kindle Unlimitedにはない良書が聴き放題になっていることも多い。有料の本もありますが、無料の本だけでも十分聴き倒せます。
ちなみにわたしは両方契約しています。シーンで使い分けているのと、両者の蔵書ラインナップが被っていないためです。
どちらも30日間は無料なので、万が一読みたい本がなかった場合は解約してください(30日以内であれば、仮に何冊読んでいても無料です)。
そして読書は、早く始めた人が圧倒的に有利。本は読めば読むほど、複利のように雪だるま式に知識が蓄積されていくからです。
ガンガン読んで、ガンガン知識をつけて周りに差をつけましょう!
とりあえず両方試してみて、それぞれのラインナップをチェックするのがオススメです!